2005 07 芸術 Art
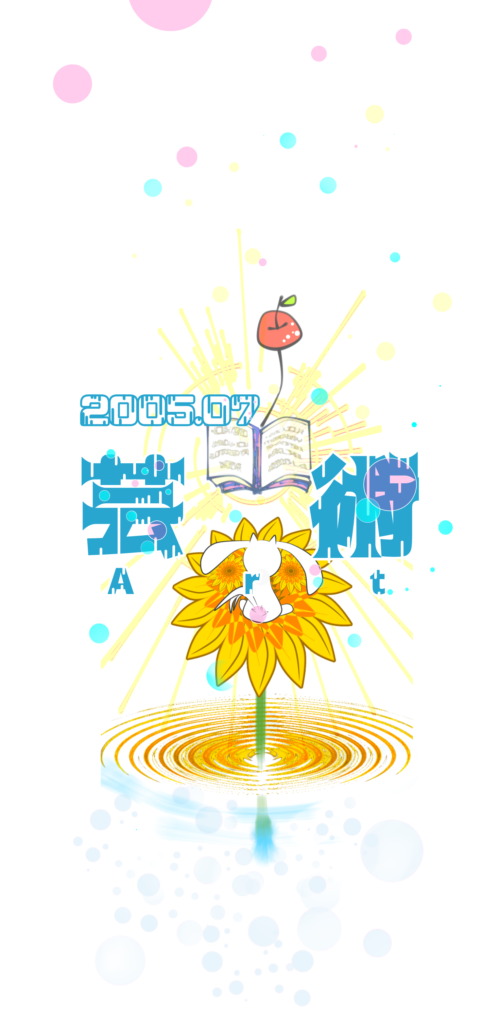
朝目を覚ますと、時計が7時40分を指していた。僕はアナログ時計が好きだ。ぱっと見るだけで時間がスムーズに頭に入ってくる。いつも通りにスムーズに時間が頭にインプットされたとき、事態のやばさに気づいた。
今日はプリミティーボのメンバーとゴッホの展覧会に行くことになっている。彼らはなぜかこういう日でさえ活動時間が早い。集合は最寄り駅に午前8時ということになっていた。
急いで着ていたジャージとスウェットを脱ぎ捨て、適当に洋服を引っ張り出す。色合いなどを考えている余裕はないはずなのだが、それでも少しは気になるお年頃だ。無難な色を組み合わせ、急いで家を飛び出した。
駅に着くともう、潤平と畑中さん、それに結城さんがいた。太陽を背におはようと右手を挙げる畑中さんはとても爽やかなのだが、妙に違和感がある。彼の格好は誰がどう見てもロックバンド歌手で、髪の毛もこれでもかというぐらいに直立に立てていることが原因だと思う。実際に、畑中さんはバンドをやっている。早朝とロッカーのコントラストは今から見に行くゴッホも越えるかもしれない幻想的な空間を創り出していた。
ゴッホ展はとても興味深いものだった。そういう感想がカッコいいと自分では思っている。俺は「夜のカフェ」という絵が気に入って絵葉書を買った。直感で好きだと思った絵が実はとてつもなく有名な絵だったことをしばらくして知った時の羞恥心は想像にお任せする。美術館を出た後は、ごく自然な流れで昼食をとることにしたのだが、ここで神が目覚めることとなる。いや。俺が目覚めさせたようなものか。
「達也って見かけによらず、けっこう絵とか描いとんよな?」
「まあ、落書き程度ですけど、気が向いたときに描いてますよ。」
「じゃあ今度気が向いたら俺のCDのジャケットの絵描いてくれよ。」
「え?CD出すんですか?」
「まあね。予定、予定。」
「あ、曲できたんですか?」
「いや、なんかこう降りてこなかった。ゴッホあかんわ。」
畑中さんはとても楽しそうだ。そもそも今日の企画は彼で、行きたい理由は「そろそろ音楽人としてゴッホあたりで一曲作らなきゃならない」とお告げがあったかららしく、今日はその材料集めということなのだ。
俺が趣味で落書きをしているのを知っていたので、俺にも声がかかったというわけだ。
「そういえば、達也って本もけっこう読んでるんだよね?」
結城さんが話題を変える。彼は社会人でもともとうちの大学とよく交流のある近くの大学の出身であるということは知っていたが、それ以上のことは僕は知らなかった。
「数は読んでますけど、内容は偏ってます。漫画みたいな小説ばっかですけどね。」
僕は正直に答えた。
「へー。今は何読んでるの?」
俺はこの時少し変わったものを読んでいた。俺は映画が好きだったのだが、「映画を見るには背景知識が必要である。」とどっかの有名な監督がインタビュアーに答えていたことを真に受け、まずは手っ取り早く聖書を読もうと思ったのだが、なんせ退屈で長いので、最近ちょうど要約版という素晴らしき本と出会い、それを読んでいるところだったのだ。
「今は聖書もどき読んでます。」
俺は笑ってもらうつもりだった。が、誰も笑わなかった。
「え?聖書興味あるの?」
「まあ。映画見るためだけですけどね。少しは読んどいた方が良いかなと思って。」
「そうなんや。大学生の時から僕も読んでるんだよね。」
「すごいですね。聖書って難しくないですか。」
「いやいや、あれはね、読み方があるんだよ。良かったら今度教えてあげるよ。」
「読み方?ですか?」
「そう。いつ暇?」
これが彼らを目覚めさせた瞬間であるとはその時の俺は微塵も気づいていなかった。やたら熱心に約束を取り付けようとする彼に圧倒され、結局は言われるがままに、結城さんに聖書を教えてもらうことになった。
当日、なぜか呼び出されたのはプリミティーボのマネージャーの住むマンションだった。最初は結城さんとマネージャーが付き合っているのかと思ったが、そうではないようだ。そのマンションには他にも女性が二人住んでいるとのことだった。ルームシェアというやつだ。
部屋に通されると、マネージャーがお茶を出してくれた。座布団が3枚横並びに置いてあり、3人が横一列に座るようになっていた。3人というのは結城さんと潤平と、僕だった。潤平は僕がサークルの人物と練習以外で会うときには必ず付いてくる。とりあえず、お茶を飲んだ。
しばらくすると、部屋にマネージャーとは違う一人の女性が入ってきた。
彼女はスタスタと笑顔を作りながら僕らの前にやってきた。結城さんが紹介してくれた。
「彼女は直子さんです。」
「どうも。始めまして、ビューティー直子です。」
斬新な自己紹介に戸惑う。
「あ、平山です。」
「下の名前は?」
「達也です。」
「オーケー、達也君ね。」
ビューティー直子は正直言って見た目は普通で、どちらかというと地味な方だ。
どこがビューティーなのかさっぱりわからないが、モデルサークルというよくわからないもののリーダーをやっていると自己紹介を、受けた。モデルサークルなんて聞いたことがない。歩き方か何かの研究でもするのだろうか。
いずれにせよ、変な人と関わってしまったという気持ちになった。
彼女は呆気に取られている俺のことは全く気にせず、部屋の隅からホワイトボードを引っ張って来た。そして当たり前のように言った。
「では、はじめましょうか。」
状況を理解していない俺とは対照的に潤平と結城さんはノートと、なにやら分厚い本を取り出していた。聖書だった。聖書からはカラフルな付箋がところどころはみ出ている。
「あ、達也君は持ってないよね。これ貸してあげるから。」
と彼女は自分の聖書を差し出した。
想像していなかった展開の中で、聖書を受けとりながらようやく気付いた。
これは、これはちまたで噂の「宗教」だと。
親だったか、高校の先生だったかに「大学内にも変な宗教があるから気をつけなさい」と注意されたあの「宗教」だ。
第何章のなんとかってところを開いてくださいという彼女の指示通りにスムーズに聖書をめくる二人、彼らはすでに信者なのだろうか。それともこれが宗教だとはまだ気づいていないだけなのだろうか。
聖書は比喩で書かれていると主張し、好き勝手に解釈していくビューティーの話は一見、論理的であるがよく考えるとおかしい。大前提として聖書が比喩で書かれているという証明が成されていないのだから当然であるのかもしれない。そんな関係ないところに思考をめぐらしていたにも関わらず、その時間はとてつもなく長いものであった。
2時間近く経って、ようやく講義が終わったが、今度はお茶会のようなものが始まった。帰りたかったが、完全に雰囲気に呑まれ、ただただ質問されたことに答えたり、「神様に頼んだら、本当に車が手に入ったんだ。こんな現実的な神様がいるなんて。」と目を輝かせている結城さんの神業話を聞いたりするしかなかった。
サンタさんにゲームが欲しいってお願いしたら、ゲームくれたのと喜んでいる幼稚園児と大差ない喜び方の彼はある意味幸せなのかもしれない。
そもそも、結城さん、あんたが教えてくれるんじゃなかったのか?何必死にノートとってんだよ。知らない部屋の天井を見上げながらなんだかよくわからない世界が世の中にはあるものだと思った。
いっしょに夕飯をたべないかという誘いを断り、やっと解放された帰り道、仕方なく夕飯を断っていっしょに聞いた。
「潤平はいつから聖書教えてもらってるの?」
「半年ぐらい前からかな。今日は復習って感じ。」
「そっか。あれ、何か変な宗教じゃないのか?」
直球をぶつけてみた。
「まさか、ただの勉強会だ。宗教とかって献金とかしなきゃだめなんだろ?俺は実際に今まで一円も払っていない。」
違和感を感じながらも、もう行きたくないなと俺は思っていた。
しばらくして、練習の後に結城さんから声をかけられた。俺はなんとなく断り切れず、二回目の勉強会に参加することにした。
しかし、俺も一つだけお願いをした。勉強会はうちでしてほしいと。
結城さんは快く了承してくれた。
そして、二回目の勉強会はうちで開催された。聖書は大学の図書館から借りてきた。
二回目も、一回目と内容は違ったが展開は同じだ。一つの文章を抜き出し、どのような比喩なのかというもっともらしい解説をしてもらった。
結城さんが帰ったあと、うちに残った潤平に再度聞いた。
「これ、宗教だろ。」
潤平は少し不機嫌になった。
「違うって言ったろ。」
「サークル全体でやってるんだろ。」
「サークルは関係ない。あくまで個人的だ。嫌ならやらなきゃ良いだろ。結城さんだって仕事が忙しい中時間を取ってくれてるというのに失礼だ。」
彼の主張は、もっともだ。
「わかった。もう参加しない。俺からは断りにくいから、潤平から伝えといてくれ。」
「わかった。」
「プリミティーボが関係ないならサークルはやめないから、こういう話は今後一切しないでくれ。次にこういう話を持ちかけてきたら俺はやめるからな。」
あまり突き詰めて、このサークルを抜けるのももったいない。このサークルでは大学にしてはめずらしくフルコートの試合ができたからだ。
結局、ただサッカーをやる場所さえくれるならこの人たちが何を信じてたって構わないと思うことにした。
潤平は少しほっとした表情を作って帰っていった。
改めて考えるとこれは何かしらの宗教活動だろう。誰が説明してもある程度同じような説明ができるのは、何かしらの体系化されたものがあるからに違いない。組織的な感じがしするのだ。
もし、宗教だとしたら、誰が信者なのだろうか。
状況的に考えて結城さんと潤平は信者だろう。ということは、あのサークルに所属している人は全員と考えるのが妥当だろうが、普段の言動からして馴染んでない人も何人かはいるが、彼らは信者なのだろうか。
プリミティーボは、人の悪口は一切言わず、周りの人を褒め続ける、聖人君子みたいな人が多くいる。なんと言うか、直接見るのが照れ臭くなるほどキラキラした純粋な目をしているのだ。あの眩しさは神の後光だったと考えれば、妙に納得がいった。
そうなると、誰が信者なのかの答え合わせをしたい気持ちが大きくなってきた。直接本人に聞くのはリスクがある。もし相手に嘘をつかれた場合、二度と判断のしようがなくなる。警戒もされるだろう。
とりあえずは客観的な人物に聞いてみようというアイディアが浮かんだが、そんな人物がどこにいるというのだろうか。
俺はベランダで日が沈んでしばらく経つのに泣き止まないセミの声を聞きながら考えた。


コメント